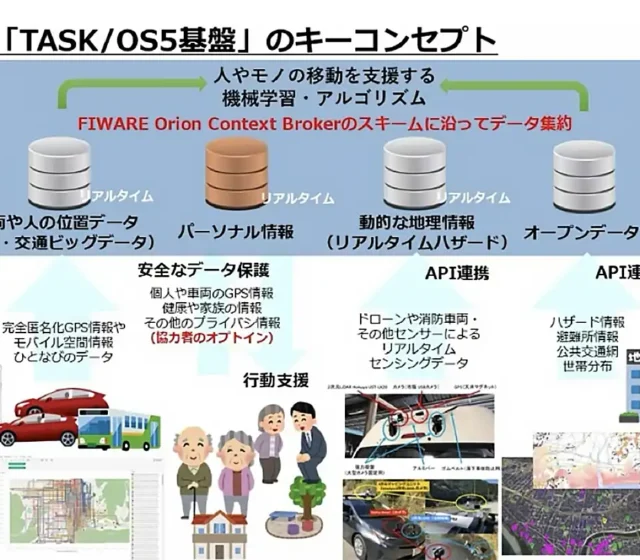山口 容平 准教授 大阪大学 大学院工学研究科
研究トピック:地球資源工学、エネルギー学、建築環境、建築設備
研究キーワード:気候変動緩和、地球温暖化対策、CO2排出量推計シミュレーションモデル
「生活様式の変容を見据えた気候変動対策」
●CO2削減も防災につながっていく

研究分野は、地球温暖化対策。つまりCO2の削減、温室効果ガスの削減による気候変動緩和がテーマです。政府はCO2排出量の削減目標を、2030年に2013年比で46%削減、2050年にはゼロにする目標を掲げました。これを実現するには、社会のあり方を変える必要があり、どう変えるかを分析し評価する研究です。具体的には、住宅・建築物で消費されるエネルギーの推計のためのシミュレーションモデルを用い、今後の技術開発などが社会全体に及ぼす影響なども含め、日本全体の変化予測も行います。研究成果は、環境省など国の政策に反映することになります。
気候変動は自然災害を増加させると考えられていますし、災害時には地域のライフライン含め、社会のエネルギー基盤のあり方が問われます。気候変動の緩和策として太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが普及し、エネルギー基盤は分散化・多様化の方向に進んでいますが、防災の関係から考えると、災害時・非常時であっても安定的で安全であるシステムである必要があります。これを実現するためには、将来普及するであろう電気自動車の蓄電池の活用も有効であると考えられています。こうしたエネルギー需要と消費のあり方を、社会全体としてどう選択するかは「新たな防災」を考える観点のひとつではないでしょうか。
●社会のあり方を選択する幅を広げること
気候変動の分野では、“Low energy demand scenario” (LEDシナリオ)という将来の道筋が示されています。IPCC(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)は7年に1回、気候変動に関する科学的知見をとりまとめて統合報告書を発行していますが、そのなかでもLEDシナリオが紹介されています。思い切って暮らしを変えることに踏み込んだシナリオで、人として品位ある暮らしが保てるベーシックな生活水準を考え、デジタル化などの新しい技術を取り入れて実現される「エネルギーや資源の投入が小さい社会」を描いています。LEDシナリオはこれを全世界で実現した場合、地球温暖化を1.5℃に抑え、気候変動による影響を低い水準に抑制することが可能であることを示しました。単純に昔に返るのか、生活上の制約が大きくなるのか、という短絡化がされることもありますが、決してそうではありません。社会のあり方の新たな選択肢です。
CO2排出量を減らすことは、不便な制約ではなく、社会に新しく加わった価値であり新しい生活の前提です。人間の歴史は、そういう前提の広がりによって常に新しいライフスタイルを選択し続けてきたのですから。
気候変動緩和には、そういう選択肢の幅を広げ、生活を変えていく人が増えることが必要になっています。それが社会のエネルギー需要を変えていく。非常時の対応方法のみでなく、有事も安心できる良いコミュニティの暮らし方を平時の防災とみる考え方があります。気候変動緩和でもそれは同じで、環境影響に通じる心地よい暮らし方を考えることだと思います。
●研究者にとどまらない多様な連携に期待
このプロジェクトでどんなことができるか、まだ分かりません。ただ、防災や気候変動緩和など新しい価値をテーマに研究の前提を広げてみることで、面白いことができる連携もあるかもしれません。その際には、ある種の共通理論があると分野を超えて考えやすいでしょうね。
また、このエネルギー需要の研究では、総務省のデータをもとに人々の日々の暮らしのシミュレーションを用いています。最近は、携帯の位置情報も加わり、時間の使い方や他者との接触状態などより詳細な記述ができるようになりました。それらは防災の研究にも活かせるのではないかと思います。
そして研究者のみでなく、よりよい社会変化や社会トレンドに敏感な方々(例えばアートや福祉の分野など)への発信や連携の機会が得られるならば、新しいライフスタイルを広く一般の人々が選択しやすくなるヒントや道筋を見つけていけるかもしれないと期待しています。
取材日:2023年9月11日