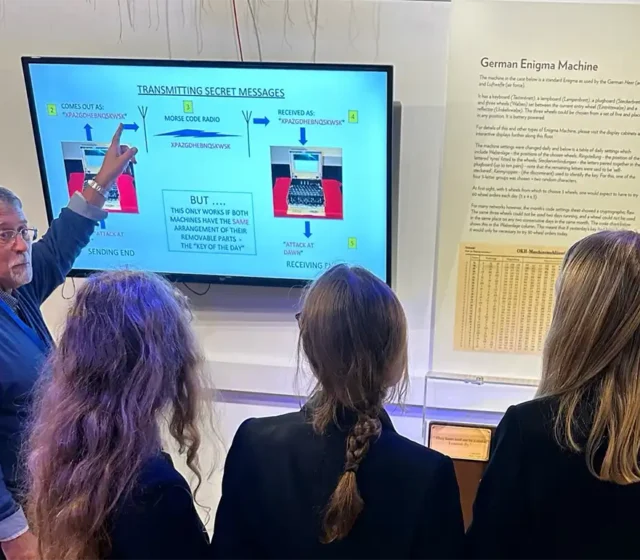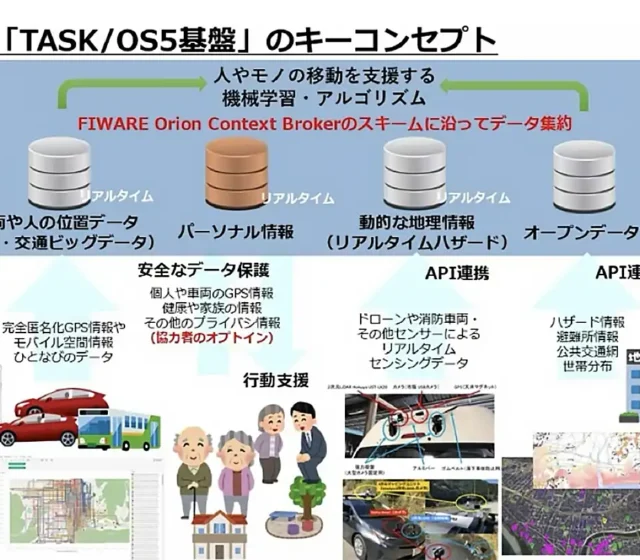入江 政安 教授 工学研究科 地球総合工学専攻
研究内容・専門分野:社会基盤(土木・建築・防災)、水工学
キーワード:河川工学、都市水環境論、環境水理学
「防災における土木の重要性の理解浸透へ」
●土木や防災をめぐるマクロとミクロ2つの視点
私の研究室では、水環境を軸に水に関連した社会基盤工学分野をテーマに据えています。健全な水環境を創造し維持していける社会システムをどのように構築するか、例えば、都市河川の汚染状況を解析し、将来の気候変動予測なども考えつつ、改善策・適応策の評価なども行っています。防災に関しても、こうした社会基盤の整備、土木という公共事業・公共政策の観点で考える立場になります。
災害への対応、被害の終息を考える際、マクロとミクロ、2つの視点があります。大規模な震災においては、最初はまず画一的なマクロな対応が優先されます。災害弱者の方の問題など被災者個々の事情に目を行き届かせるといったミクロな視点は、それとは別のフェーズということになります。優劣の問題ではなく、2つの視点は共に大切です。常に同時に進行される必要があります。
災害に限らず、土木は公共政策であり、平常時は、基本的にマクロ視点に軸足を置きます。防災あるいは減災策として、例えばダム開発などの大規模な公共事業で全体の被害を抑止するというマクロ視点があり、そうした開発の環境影響をどう考えるか、環境破壊に対する代償措置など個々の視点、ミクロの視点があると思います。
現在メディアの報道は実感しにくいマクロの視点にあまり触れずに、肌感覚に近い、あるいはわかりやすいミクロ視点からの情報になりがちで、ネット上で個人の発信機会と加速的に情報が急増して、土木をめぐってもミクロ視点の議論に終始する印象があります。マクロ視点での問題提起や提案がないままに、批判の対象にすらなりがちな状況には危機感を覚えています。
●“人を守り、救う”のが土木の目的
そもそも、土木は「人を守る」「人を救う」「人の生活を向上させる」のが目的であり、揺るがない基本姿勢です。
自然災害から多くの人の生命と財産を救うためには、自然環境に手を加える開発というマクロな政策も有用で、必要となる場合が少なくありません。実際に、反対運動を受けてダム開発を過去に中止した地域において、数年前に河川の氾濫が起き、多数の死者を含む被害が生じたケースがありました。ミクロ視点では確かに様々に切実な課題はありますが、一方で全体を救うマクロ視点での対策も必要であることの証左です。公共の政策を担う公務員の数が減少し、現実の被災地で活動する自衛隊の方々はじめ、組織で動く立場の姿や意見は顕在化されず、こうしたマクロ視点の意見や議論が見えにくいという難しさもあります。局所最適解にばかり陥らずに、全体最適をどう実現するかが大切だと思います。公共事業への信頼が醸成されにくい状況下、土木分野の専門家の役割と責任は重くなっています。
●防災における土木の意義を語る場を
「新たな防災」への参画によって、多様な専門分野の方々の考えからの気づきはあります。学際的な連携という点でも、以前から土木分野では経済学分野の方たちとやってきた経験がありますし、私たちも社会学分野と同じ弧を描きながら、共通の未来社会に向かうイメージがあります。
このような場を通じて、単純に二項対立で捉えて個々の立場で閉鎖的になる状況を変えられればと思います。ミクロ視点での議論が目立つコミュニケーション環境において、対立構造を避けながら、学外をはじめ多様な分野の方と関わり、土木分野の意義や有用性に関して理解を促進する機会が得られると良いなと考えています。
取材日:2023年3月6日